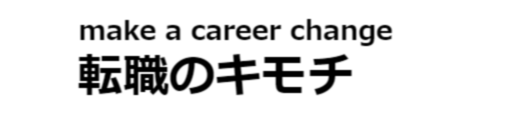紆余曲折、やっとの想いで最終面接まで進んだのに不採用...
「なぜ!?」と叫びたくなるでしょうし、ショックは大きいですよね。
でも、
- 転職の最終面接は普通に落ちる!
- 転職の最終面接は落ちる確率の方が高い!
まず、この事実を頭に叩き込んでおきましょう。
風潮的に「最終面接は顔合わせだ」「余程のことがない限り落ちることはない」というニュアンスで語られることがありますが、それは検討違いです。
新卒採用なら少しはそういった側面もありますが、こと転職においては全く当てはまりません。
![]()
新卒採用は何十名、何百名を採用するので最終に進んだ人の多くが内定となりますが、中途採用は適材適所の限られた人数しか採用されません。
採用人数は1~2名なんて会社が圧倒的多数を占めます。
実際、最終面接まで進んだ人の内定率は30%前後と言われているので、不採用となる確率の方が高いことが分かります。
つまり、最終面接は単なる顔合わせの場ではなく、選考の場である!
そういうことなんですね。
ここでは、最終面接が選考の場であることを前提に、「何故ここまで来て落ちてしまうのか?」という視点から理由と心得をお伝えします。
- 油断が不採用を招く
- 雰囲気の違いに圧倒される
- 面接担当者の視点の違いを理解していない
- 的外れな逆質問で認識の甘さを露呈
詳しく見ていきましょう。
1.油断が不採用を招く
少し精神論的な部分になりますが、最もやってはいけないのが「油断」です。
人間とは不思議なもので、油断しているとそれが行動や言動に出てしまうんですね。
つい軽はずみな発言をしてしまい、「その一言が原因で不採用」なんてことがよくあります。
冒頭でも述べましたが、最終面接も「選考の場」であることを認識し、気を引き締めて面接に臨みましょう。
最終面接で失敗する人の思考
- 最終面接は顔合わせだから心配無用だろう
- 大きな失敗さえしなければ採用されるだろう
- 最終面接に新たな対策は不要だろう
- これまでの感触が良好だから大丈夫だろう
こんな油断があなたを不採用に導きます。
また、最終選考の場には、あなたと同等、またはそれ以上のライバルがいることも忘れてはいけません。
- 採用されると高を括って対策不十分で面接に臨んだあなた
- 油断せず万全の準備をもって面接に臨んだ強力なライバル
どちらが採用されるかは言わずもがなですよね。
最終面接までの感触が良かろうが、そんなことは忘れて下さい。これまでの経過は合否に全く関係ありません。
最終面接までの担当者に気に入られてようが、それも忘れて下さい。採用決定権は持っていません。
重要なのは、最終面接で採用決定権を持った重役(社長)にそれを示すことです。
絶対に油断禁物です。
2.雰囲気の違いに圧倒される

一般的に最終面接は「社長(経営者)」や「役員」など、最終決定権を持った重役が担当します。
まずここで一つ認識しておくべきは、重役達はこれまでの面接官とは雰囲気が違うという事実です。
更に最終選考の場であることも相まって、「これまで以上に雰囲気がピリっとしている」ということが多いのです。
- 一次面接 ~ 和やかな雰囲気
- 最終面接 ~ ピリついた緊張感たっぷりの雰囲気
そんな時に陥ってしまうのが「雰囲気にのまれ、これまでの自分が出せない」といったパターンです。
その結果、上手く話せない、どもってしまう、頭が真っ白になる・・・。
実は、この雰囲気の違いや緊張が原因で、不完全燃焼で面接を終えてしまう人が意外に多いんですね。
![]()
これに関しては、面接に臨む際の「心の持ちよう」が重要になってきます。
最終面接はこれまで以上に緊迫感のある雰囲気の中で行われる!
これを前提に面接に臨むべきです。想定していれば、いざそのような状況に陥っても落ち着いて対処できます。
「この最終面接が終われば転職活動から解放される!!」
- こんな気持ちで浮ついていませんか?
- 一次面接の時のように、緊張感をもって臨んでいますか?
- ここまでくれば大丈夫だと高を括っていませんか?
経営層クラスには全て見抜かれます。
3.面接担当者の視点の違いを理解していない
一次・二次面接は「人事・現場担当者」が行い、最終面接は「社長・役員」が行う!
これが面接の一般的な進め方ですが、両者は応募者に対する視点が異なるので、質問内容や求める内容が変化します。
この事実を理解せず、「新たな対策は不要だろう」と舐めて掛かると痛い目を見ることに...。
まず、最終面接に残ったということは、以下の項目は採用基準に達していると判断できます。
- 社会人としてのマナー
- 企業文化とのマッチング
- 求めるスキル・経験・知識
だからこそ、ここまで落ちることなく辿り着いたんですね。
では、最終面接では何を見られるでしょう?
それは、ビジョン(将来性)です!
社長や役員は会社の経営者であり、会社を永続的に成長・存続させていく使命を背負っています。
ゆえに、短期的な業績アップや、直近の企画提案だけではなく、長期的に会社に貢献してくれる人材に入社してほしいと考えてます。
要は、人事や現場担当者のように、直近の配属先や即戦力性だけを見ているわけではないということ。
![]()
そのため、最終面接では「ビジョン(将来性)」に関する質疑応答がなされることが多いのです。
例えば、以下のような「未来を見据えた質問」が投げかけられます。
- 当社を志望した理由を教えていただけますか?
- 当社に入社したら、どんな仕事をしていきたいですか?
- 今後のキャリアビジョンについて教えて下さい!
- あなたは〇〇年後、どうなっていたいですか?
- 今後の業界の見通しについてどう考えていますか?
- あなたから見た当社の課題は何だと思いますか?
- あなたが当社の社長だったら何をしますか?
志望動機は最終面接でも問われることが多く、高い入社意欲を示すと共に、「将来的にどう貢献していきたいか」までを合わせて語りたいですね。
キャリアビジョンを持っておくことも大切で、5年後、10年後、20年後まで想定しておきましょう。更には、「業界全体を捉える視点」や「経営的な視点」についても準備が必要です。
これが経営層の面接なので、これまでの面接と同じ問いだったとしても、将来性を意識した答えを示すことです!
一次面接の段階で対策できていれば問題ありませんが、「ビジョン(将来性)」が薄いと感じる場合は、最終面接前にしっかりと準備しておきましょう。
4.的外れな逆質問で認識の甘さを露呈

最終面接でも大抵は「逆質問の場」が最後に設けられます。
ここで、社長や役員に対して、以下の質問はしないことです。
- 細かな人事制度
- 配属部署の仕事の進め方
- 福利厚生
- 給料
これは、一次・二次面接で解決しておくべきことであり、経営陣に聞くことではありません。
最終面接の逆質問は「経営戦略」や「将来ビジョン」に関する質問をするのが一般的です。
また、「質問はありません」という回答は入社意欲を疑われるので避けましょう。
私の失敗
私は、社長による最終面接で「一次面接で聞きたいことは全て聞いたので、特にありません」と回答したことがあります。
これが直接の原因かどうかは分かりませんが、不採用という結果になりました。
面接後に非常に後悔しましたので、同じ過ちは犯さないよう注意して下さい。
まとめ

最終面接で落ちる「4つの理由」についてお伝えしてきました。
全ての要素を総合して考えると、最終面接を理解していないことから誘発される「準備不足」が原因ではないでしょうか。
要は、最終面接を勝ち抜ける体制が整っていないということ。こんな状態でライバルに勝てるはずがありません。
私は2回目の転職の際、最終面接で4連敗した経験があります。
今振り返ると完全に「準備不足」が原因でしたね。
最終面接まで進んだことに浮かれ、「内定確実だろう」と高を括って対策せず、見事に跳ね返されたということです。
![]()
どんなに対策を施そうが、ライバルがいるので落ちる時は落ちます。
ただ、万全を期さずして落ちた時は「後悔」が生まれるので、決して最後まで気を抜くことなく、万全の準備で最終面接に臨んで下さい。
それが結果的にあなたへ「内定」を届けてくれるはずです。
最終面接情報
最終面接では、将来性と共に「人間性」も深く探られます。
あなたがどんな人間なのか、社風にマッチするのか、どんな考えを持っているかなどですね。
一般的な質問で探られることもあれば、雑談・世間話を用いられることもあるので、興味のある方は「面接で雑談・世間話が取り入れられる理由」ページも合わせてご覧下さい。